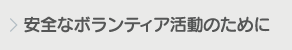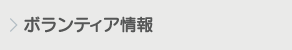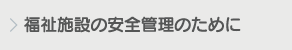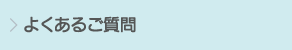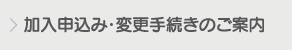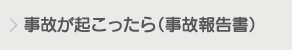ボランティア活動保険に関するQ&A
加入手続きについて
- Q1. ボランティア活動保険の補償期間を教えてください。また、中途加入した人の補償期間はどうなりますか?
- A1. ボランティア活動保険は毎年4月1日午前0時から翌年3月31日午後12時 (24時)の1年間が補償期間となります。また、中途で加入された場合も3月31日で補償は終了しますので、翌年は4月1日からの更新手続きが必要となります。
- Q2. 最寄りの社会福祉協議会で加入申込みをするようにパンフレットに記載されていますが、「最寄り」とは、居住地(現住所)、勤務先、活動場所のいずれでも構わないのですか?
- A2. 「最寄り」とは、居住地(現住所)を指していますが、勤務先や活動場所などの社会福祉協議会で会員登録などの受付が可能であれば、そこでも加入手続きは可能です。事前に該当の社会福祉協議会までお問い合わせください。
- Q3. 複数のボランティアグループに所属してボランティア活動をしている場合、それぞれのグループで保険に加入しなければなりませんか?また、他県におけるボランティア活動であっても対象になりますか?
- A3. 複数のボランティアグループのうち、どこか1か所で加入手続きをとってください。他のグループにおける活動についても社会福祉協議会に届出されている活動であれば補償されます。国内におけるボランティア活動は対象になります。
- Q4. グループでボランティア活動保険に加入する場合、「加入申込書」に加入者全員の氏名を記入しなければいけませんか?
- A4. グループですでに作成済みの名簿がある場合は、「加入申込書」に名簿のコピー(名簿の様式は問いません。)を添付して社会福祉協議会に提出すれば、「加入申込書」に加入者氏名を記入する必要はありません。
- Q5. 加入申込みの手続きに来ましたが、印鑑を忘れてしまいました。加入手続きは可能ですか?
- A5. 加入申込人が法人や地方公共団体の場合は、法人印や公印の押印が必ず必要になりますが、グループや個人の場合は、加入申込手続きに来た方個人の署名(フルネーム)でも可能です。
ボランティア活動保険の加入対象になりますか?
- Q6. 親子でボランティア活動を行っていますが、小・中学生も加入できますか?
- A6. 小・中学生も、本人の意思でボランティア活動を行う場合は、加入できます。賠償事故で責任能力がないと認められても、監督義務者を被保険者に追加しておりますので補償の対象となります。
〔監督義務者を被保険者とする理由〕
近年、ボランティア活動が一般化し、小・中学生によるボランティア活動が活発化していますが、小・中学生による加害行為の場合、責任無能力(※)を理由として加害行為者本人に責任が発生せず、監督義務者が損害賠償責任を負うことがあるため、監督義務者を被保険者としたものです。 - Q7. 災害ボランティア活動を主な目的とするボランティアでも、加入できますか?
- A7. 社会福祉活動の一環として行われる災害ボランティアも加入できます。地震などの被災地でのボランティア活動については、地震・噴火・津波によるケガを補償する天災・地震補償プランに加入されることをお勧めします。
なお、海難救助や山岳救助などのボランティア活動は補償の対象となりません。
(災害ボランティア活動の場合は被災地の社会福祉協議会またはボランティアセンターから委嘱された活動であることが必要です。) - Q8. 行政から委嘱された活動は、ボランティア活動保険の加入対象になりますか?
- A8. 行政から委嘱された活動の場合、無償の活動である場合、または交通費や昼食代などの実費弁済のために費用が支給されることが規定に明記されている場合は、対象としています。
- Q9. 福祉学科の学生ですが、福祉施設でボランティア活動をすれば単位が取得できます。ボランティア活動保険に加入できますか?
- A9. 免許、資格、単位などの取得のために行うボランティア活動は、自発的な意思によるものとはいい難く、対象になりません。
- Q10. 地域の学校支援ボランティアとして、学習支援や部活動指導、校内環境整備や登下校安全確保などの活動をしています。ボランティア活動保険の対象になりますか?
- A10. 対象になります。
また、自分の子供が通う学校の支援であっても、目的が学校全体を支援するための活動であれば対象になります。
ただし、部活動指導において、学生・生徒とともに競技を行っている際の事故は対象になりません。 - Q11. NPO法人に所属するボランティアが行うボランティア活動は加入の対象となりますか?
- A11. 社協が認める活動は対象となります。全社協のボランティア活動保険では、NPO法人に所属するボランティアが行うボランティア活動にも対応できるよう、「特定非営利活動促進法(NPO法)」に規定されている日本国内における活動を加入対象としてます。ただし、対象となる活動は、「特定非営利活動促進法(NPO法)」第1章総則第2条(定義)第1項に規定する活動(同法の別表記載の活動)に限定されており、NPO法人の事業全体を対象としているものではありませんのでご注意ください。
- Q12. 高齢者の心を和ませる活動として、赤ちゃん連れで老人ホームの慰問活動をしますが、赤ちゃんはボランティア活動保険の対象になりますか?
- A12. この保険の対象になるのは自発性のある活動ですので、ボランティア活動保険の対象にはなりません。
- Q13. 日本国内でボランティア活動をする外国籍の方も加入できますか?
-
A13. 加入申込人の条件(社会福祉協議会およびその構成員、会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体)を満たしていれば加入できます。ただし、以下の条件がありますので、ご注意ください。
- 日本国内のボランティア活動のみが対象です。
- 傷害補償については、日本における「医師法上の医師」の診断・治療を受けた場合のみが対象になります。
- 本人と連絡が取れる日本国内の連絡先が必要です。( 可能であれば、本国の居住地・連絡先もあわせてご提供ください。)
- Q14. 自治会、青年団などで組織する自主防災組織(初期消火活動または防火活動など)は加入対象になりますか?
- A14. 自治会や青年団としての組織活動であれば加入できません。ただし、自治会、青年団などの中から自発的な意思により組織された団体であれば、加入対象になります。
- Q15. 町の小学校では総合学習の一環で、授業時間や放課後に地域の有志の方々に昔の遊びを教えてもらったりしています。学校管理下でのボランティア活動は、ボランティア活動保険の対象にならないとなっていますが、この地域の有志の方々はボランティア活動保険に加入することはできますか?
- A15. 加入することができます。学校管理下でのボランティア活動がボランティア活動保険の対象とならないのは、その活動をしている人が、学校の教職員や生徒の場合です。今回の質問のように、学校外の人が行うボランティア活動は、たとえ学校の管理下であってもボランティア活動保険の対象になります。なお、福祉科目など学校の教育課程における授業で講義を行う場合であっても、学校と雇用関係になく、自発的な意思によりボランティアとして行うものであれば対象になります。
- Q16. 市民後見人をしています。ボランティア活動保険の対象に加入できますか?
- A16. 市民後見人は、財産管理を行うなど24時間がその活動時間となり、日常生活との区別が困難なため、ボランティア活動保険では加入の対象にしていません。
- Q17. 調理専門学校の学生がレストランで調理ボランティアをしています。ボランティア活動保険の対象になりますか?
- A17. 目的が「自分の調理知識、技術習得のための活動」であり、「他人や社会に貢献する活動」とは言い難いことから、加入対象になりません。また、「レストラン」という生業のお手伝いも対象になりません。
- Q18. ボランティア活動に興味があり、勉強会に参加したいと思います。ボランティア活動保険に加入できますか?
- A18. 加入できません。ボランティア活動保険で対象となる勉強会は、ボランティア活動を行うための準備として、ボランティア活動団体で計画されたスケジュールや内容に基づいて行われるものが対象です。ボランティア個人の判断によるスキルや知識習得は自己研鑽に該当し、ボランティア活動保険の対象となりません。
- Q19. 学校教育の一環として教職員や生徒が行うボランティア活動は、ボランティア活動保険の対象になりますか?
- A19. 学校が教育計画の一環として行う場合は、学校管理下の活動のため対象となりません。ボランティア活動保険の対象は、そのボランティア活動が「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償の活動」で、「学校管理下外の活動」です。学校の管理下とされる次のような場合は、対象となりません。
学校の管理下となる場合 例えば 1. 学校が編成した教育課程に基づく授業中 ・ 各教科(科目)・道徳の授業中、幼稚園での保育中
・ 特別活動中(児童・生徒・学生会活動、学級会活動、ホームルーム、学級指導、クラブ活動、儀式、学芸会、運動会、遠足、修学旅行、大掃除など)2. 学校の教育計画に基づく課外指導中 ・ 部活動、林間学校、臨海学校、夏休みの水泳指導、生徒指導、進路指導など 3. 休憩時間中 ・ 始業前、業間休み、昼休み、放課後 4. 通常の経路、方法による通学中 ・ 登校(登園)中、下校(降園)中 5. 学校外で授業等が行われるとき、その場所、集合・解散場所と住居・寄宿舎との間の合理的な経路、方法による往復中 ・ 鉄道の駅で集合、解散が行われる場合の駅と住居との間の往復中など 6. 学校の寄宿舎にあるとき 7. 定時制、通信制の高等学校生徒が技能連携施設で教育を受けているとき - Q20. 夏休みを利用して体験ボランティアに参加します。ボランティア活動保険の加入の対象になりますか?
- A20. 対象になりません。体験ボランティアは、活動者自身の経験のためという目的が含まれると考えられるため、ボランティア活動保険の加入の対象にはしていません。ただし、ボランティア活動保険への加入要件を満たしており、かつ、社協が地域の福祉などのために支援を行う体験ボランティアであれば対象としています。
補償対象となる活動・補償範囲について
- Q21. 基本プランと、天災・地震補償プランの違いはどのようなものですか?
- A21. 「基本プラン」は、ボランティア活動中のケガと損害賠償責任を補償するプランですが、天災(地震・噴火・津波)によるケガは補償されません。
一方、「天災・地震補償プラン」は、基本プランの補償範囲だけではなく、天災(地震・噴火・津波)によるボランティア自身のケガをも補償するプランです。 - Q22. 台風災害時のボランティア活動は、どちらのプランを選べばいいですか?
- A22. 台風や竜巻などの風水害による活動中のケガは、基本プランでも補償されます。
天災・地震補償プランに加入していないと補償されないのは、ボランティア活動中に①地震、②噴火、③津波によりケガをした場合です。被災地でのボランティア活動では予測できない様々な事態が想定されます。活動中の二次被害の備えとして、あらかじめ天災・地震補償プランにご加入いただきますと、より安心してボランティア活動に参加いただけます。 - Q23. ボランティア活動も行っている趣味のサークルです。練習中の事故は補償の対象になりますか?
- A23. ボランティア活動のための練習か、趣味の活動としての練習か、市民祭りなど発表会で披露するための練習かの区別が困難であることから、練習中は対象外と考えられます。(ボランティア活動中のみを対象としています。)
- Q24. ボランティア活動でお土産(名産品)をもらいました。そのボランティア活動はボランティア活動保険の対象になりますか?また、ボランティア活動保険の対象としている無償の範囲と、対象にならない有償について、具体的に教えてください。
- A24. 名産品など換金性のないお土産をもらう活動は有償の活動には該当しないため、対象になります。なお、無償と有償の具体的な範囲は以下のとおりです。
無償・有償の範囲(例) 無償 ●昼食代やお弁当のみが支給される活動 ●肩たたき券など換金性のないものをもらえる活動 ●交通費、昼食代等の費用弁償のみが行われる活動 ●謝礼としてお土産をもらった場合(名産品などのお土産が貰える活動。ただし、商品券など換金性のあるお土産は不可。) ●収益が出る活動(空缶のリサイクル活動など)のうち、その収益が活動者個人に還元されないもの。(昼食などでの還元は可。) ●行政または社会福祉協議会が運営する制度でポイントが付与される活動 有償 ●活動の報酬、対価として謝礼が支払われる活動(金額の大小は問いません。交通費としてなどと明確にされていなければ1円でも有償とみなします。) ●物品を購入できる地域通貨が支給される活動 ●商品券、クオカードが支給される活動 - Q25. ボランティア活動中とは、どこからどこまでをいうのですか?深夜の活動や複数の拠点を移動しながら活動する場合は対象になりますか?
- A25. ボランティア活動を行う目的をもって通常の経路により住居(住居以外の施設を起点とする場合、または住居以外の施設に帰る場合はその施設)を出発してから、住居に帰るまでの間をいいます。ボランティア活動以外の目的で行動した場合、または往復途上を外れた場合は、その時点でボランティア保険の補償は終了します。※「住居」とは、戸建の場合は敷地内、マンションの場合は玄関内(専有部分)をいいます。
- Q26. 社会福祉協議会の業務のお手伝い(配食サービスなど)をしているときに利用者にケガをさせてしまいました。ボランティア活動保険で補償されますか?
- A26. ボランティア個人の行為に過失があった場合には、個人責任を問われる可能性がありこの場合にはボランティア活動保険で補償されます。なお、一般的には使用者である社会福祉協議会が、利用者に対して損害賠償責任を負うことになりますので、社会福祉協議会が契約している賠償責任保険(全社協の補償制度では「社協の保険」、「福祉サービス総合補償」)で補償されることになります。
- Q27. ボランティア活動保険に加入しているボランティア同士の賠償事故は補償の対象になりますか?
-
A27. 対象となります。ただし、相手が
被保険者の配偶者
被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族(※)
被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚のお子様
の場合は対象となりません。
(※)親族とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族をいいます。(民法725条) - Q28. 実際に損害賠償請求されていなくても保険金は支払われますか?
- A28. 支払われません。法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金を支払います。
- Q29. ボランティア活動終了後、帰宅前に買い物のためにスーパーに向かっている途中、転んでケガをしました。この場合、往復途上として補償されるのでしょうか?
- A29. 補償されません。ボランティア活動と別の目的をもって行動を開始した時点で補償は終了します。買い物を終え、ボランティア活動場所と自宅間の通常の往復経路に戻った場合でも、一旦別の目的のために行動をしているため、対象にはなりません。
- Q30. 農作物の生産・収穫や販売等、農家の生業を手伝うボランティア活動は加入の対象になりますか?
- A30. 農家の生業支援や、農作物の販売を目的とするボランティア活動は、無償であっても農家の経済活動につながるため加入の対象になりません。
このような事故は補償されますか?
- Q31. 補償の対象となる「ケガ」とはどのようなものですか?
- A31. 急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガをいいます。
- 「急激」とは、突発的に発生することであり、ゲガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
- 「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
- 「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
- Q32. ボランティア活動保険とボランティア行事用保険で、電動工具を使用する場合に対象になる、ならないが異なっていると思いますが、詳しく教えてください。
-
A32. ボランティア活動保険で対象外になる主なものは、以下の通りです。
- チェーンソーを使用する森林ボランティア活動
- 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動 など
対象になるもの(対象外と間違いやすいもの)
- チェーンソーを使用する街路樹剪定活動
- 草刈機を使用する除草作業
- 電動ノコギリを使用する森林ボランティア活動
なお、ボランティア行事用保険では、電動工具・銃器を使用する行事は対象外になるため、上記はすべて対象外です。
- Q33. 配食・給食ボランティア活動で食事の提供を行い、食中毒が発生した場合、補償の対象になりますか?
- A33. 調理中、あるいは運搬中といったボランティア活動中に原因があった場合は補償の対象となります。
ただし、時間をおいて食べたために起きた事故は食べた人の責任ですので、対象となりません。 - Q34. ケガが原因で病気になった場合は補償の対象となりますか?
- A34. 活動中のケガと直接因果関係のある病気については対象となります。例えば転んだ時のキズが原因で破傷風になった場合などは補償されます。
- Q35. ボランティア活動中、社会福祉協議会より借りている物を誤ってこわしてしまった場合は補償の対象になりますか?
- A35. 賠償責任の補償の対象となります。修理費用もしくは時価のいずれか低い額が補償されます。
- Q36. ボランティア活動に向かう途中、ボランティア自身が自動車を運転し、事故を起こしてしまった場合、ボランティア活動保険で補償の対象となりますか?
- A36. ボランティア自身のケガは補償の対象になりますが、賠償責任やボランティア自身以外の方のケガは補償の対象になりません。(同乗者の方もボランティア活動保険に加入されていて、ボランティア活動に向かう途中であった場合は、同乗者のケガは同乗者が加入するボランティア活動保険で補償の対象となります。)
ボランティア活動保険では、自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任の補償、自動車の修理代などは対象になりません。(別途ご加入されている自賠責保険および自動車保険でのお支払いとなります。) - Q37. ボランティアのBさんは、地域の子どものキャンプに付き添った際、大きなハチに刺され、帰宅後ひどく化膿し通院しています。ボランティア活動保険の補償の対象になりますか?
- A37. 後日化膿した場合でも、その原因がボランティア活動中にハチに刺されたものであれば対象となります。ただし、単に蚊に刺されてかゆいだけなど、医師の治療を要さない虫さされはケガとはいえず、対象になりません。
- Q38. キャンプでのボランティア活動中、川で滑ってコンタクトレンズを流してしまいました。ボランティア活動保険で補償されますか?
- A38. ボランティア個人の所有物は、ボランティア活動保険の補償の対象ではありません。転倒して眼鏡や入れ歯をこわしてしまった場合も同様です。
- Q39. ボランティア活動中に熱射病になった場合は補償されるのでしようか?
- A39. 熱中症(日射病・熱射病)により身体に障害を被った場合は、補償されます。
- Q40. ボランティア活動に行こうとして自宅の庭で転んでケガをしました。この場合、往復途上として補償されるのでしょうか?
- A40. 補償されません。
往復途上の補償は、自宅の敷地を出てから自宅の敷地に戻るまでとなります。
災害ボランティアについて
- Q41. 大規模災害時の「特例」対応について教えてください。
-
A41. 全社協のボランティア活動保険では、風水害や、地震、噴火、津波などの大規模な災害の対応として、被災地社協に災害ボランティアセンターが設置された場合、道県・指定都市社協からの連絡に基づき、「大規模災害特例」の措置を適用します。(大規模災害特例の適用の有無はお近くの社協に確認ください。)特例措置が適用された場合は、翌日午前0時からではなく、加入手続き完了後ただちに補償開始となるため、次のいずれかの加入手続きにより迅速な補償がされることになります。
- 災害支援活動へ向かう前に居住地の最寄りの社協で加入手続きを行った場合、活動場所(被災地)への往復途上も補償されます。
- 被災地の災害対策本部もしくは社協で加入手続きを行った場合、手続き後ただちに補償されます。なお、被災地ではない社協が会員から災害ボランティアの加入申し込みを受けた場合は、必ず事前に被災地でのボランティア受け入れがあるか否かについて、被災地の所在する都道府県・市区町村の社協にお問い合わせいただくか、全社協の「被災地支援・災害ボランティア情報」ホームページ(https://www.saigaivc.com/)でご確認ください。ボランティア活動保険に未加入のボランティアは、できるだけ居住地の社協、またはWEB(特例で開設)から加入のうえ、被災地のボランティアセンターへ向かうようご案内ください。なお、災害ボランティア活動は、被災地の社会福祉協議会またはボランティアセンターでの登録が必要です。
- Q42. ボランティア活動保険でいう「天災」とはどのような災害のことですか。
- A42. 保険約款上、天災とは「地震、噴火、津波」をさします。台風や大雨、竜巻などの風水害は天災には含まれず、「基本プラン」でも補償されます。地震、噴火、津波に起因するケガをカバーするための「天災危険担保特約」を付加したものが「天災・地震補償プラン」です。
- Q43. 地域でのボランティア活動だけの場合は、「天災・地震補償プラン」に加入できないのでしょうか。地域でのボランティア活動だけの場合は、「天災・地震補償プラン」に加入できないのでしょうか。
- A43. 加入できます。被災地での活動に限らず、地域での活動においても天災への備えとして「天災・地震補償プラン」に加入いただければ、より安心して活動にご参加いただけます。
- Q44. 災害時の避難を支援する活動や避難所の開設への協力は対象となりますか?
- A44. 災害時の避難を支援する活動は、ボランティア活動ではなく、人命救助活動に該当すると考えられます。また、活動の開始や終了について明確な区別がつかないことから、活動中であることの証明が困難であることからも加入対象外となります。また、避難所の開設への協力は行政等の指示に基づいて行うものであり自発的な活動ではないと考えられ、加入対象となりません。
- Q45. 転居地(または他県)で活動中に事故が発生した場合、ボランティアはどこに事故報告をしたらよいのでしょうか?
- A45. 加入受付社協に連絡をしてください。
- Q46. 加入者個人に保険証券は発行されないのですか?
- A46. 保険証券は、損保ジャパンより契約者である全社協に発行され、加入者個人には発行されません。加入申込書2枚目が加入者控となり加入証を兼ねていますので、補償期間が終了するまで大切に保管してください。
ボランティア行事用保険に関するQ&A
加入・変更手続きについて
- Q1. ボランティア行事用保険の補償はいつ開始するのですか?
- A1. 加入手続き完了日の翌日午前0時以降の行事開催日から補償されます。
加入手続きの完了とは、加入申込者が保険料を全社協指定口座に払い込み、「加入依頼書」(社協確認印押印済のもの)を専用封筒にて全国社会福祉協議会「ボランティア関係保険制度」係宛に送付または提出したときとなります。 - Q2. Aプラン(宿泊を伴わない行事)の1行事の考え方を教えてください。
- A2. ボランティア行事用保険は、行事の参加者全員で加入してください。参加者とは、行事の主催者やボランティアを含む参加者の全員をいいます。
また、1行事とは、通常1日が1行事(2日なら2行事)となりますが、特例として、同一主催者が行う同一行事の日程が連続して2日間以上にわたる場合は、これを1行事とします。- 【例1】9月1日、2日、3日と同じ行事を行い、各日7名が参加する場合
1行事の参加者人数は、7名×3日=21名で加入することができます。 - 【例2】1日の参加者15名で2日連続の行事を開催し、参加者が2日とも同じ人であった場合
1行事の参加者人数は、15名×2日=30名で加入してください。
- 【例1】9月1日、2日、3日と同じ行事を行い、各日7名が参加する場合
- Q3. 加入手続き後、行事日程や参加人数が変更となった場合どうすればよいですか?
- A3. 行事日程や参加人数に変更があった場合、加入を受付けた社会福祉協議会を通じて、原則として行事開催予定日の前日までに変更手続きを行います。また、行事が中止になった場合、順延日が決まっていない場合は、翌営業日までに保険料の返れい手続きを行ってください。翌営業日までに手続きを行っていただけなかった場合、保険料を返れいできませんのでご注意ください
- Q4. 同一主催者による複数の行事の開催予定があらかじめわかっている場合、1度の加入申込みで手続きできますか?
- A4. 1枚の加入依頼書で、3件まで加入申込みをすることができます。4件以上の場合は「別紙」をご利用ください。加入手続き後、各々の行事の日程・参加者数に変更がある場合には、加入した社協にて変更手続きを行ってください。
- Q5. 参加者の都合で、日帰りの人や1泊の人また2泊の人がいます。ボランティア行事用保険はどのように加入すればよいのでしようか。
- A5. 参加者名や参加日程が確定している場合であれば、日帰りの人はAプラン、宿泊の人はBプランと、記入する行を変えて一度の手続きで加入ができます。Aプランの最低保険料は20名分です(Bプランは最低保険料はありません。)。また、宿泊日・日数の異なる参加者がいる場合は、宿泊日・日数ごとに行を変えて保険料計算をしてください。なお、Bプランは参加者名簿の提出が必要です。
- Q6. 同一の行事が同一の日に別々の会場で実施される場合の加入依頼書への記入方法について教えてください。また、特定の会場だけ加入することはできますか?
- A6. 加入依頼書の行事欄に行事名称と開催場所を明記の上、すべての会場の合計人数を記入してください。また、すべての会場が1行事となるため、特定の会場だけを加入することはできません。
行事用保険の加入対象になりますか?
- Q7. 日帰りの1日行事ですが、行事の前日にその準備と翌日に後片付けがあります。
準備や後片付けの日も含めて加入できますか? また、行事と準備・後片付けを分けて加入できますか? - A7. 準備と後片付けを含め加入できます。
1行事として行事の準備の日から後片付けの日までの参加人数の合計で加入してください。ただし、行事の日を含めず準備の日や後片付けの日のみで加入することはできません。また、行事区分が「A2」となる場合は、準備と後片付けも全て「A2」が適用されます。準備の日や後片付けの日の行事区分は行事と同一の区分になります。 - Q8. 山・森林などで行う行事の区分を教えてください。
- A8. 植林や電動工具を使用する枝はらい、下草刈り、登山用具を使用するような危険な登山などは加入対象外となります。草花を植える程度のものやハイキング、森林浴などは「A1」での加入となります。
- Q9. ボランティアグループでの懇親行事としてキャンプに行くことになりました。
ボランティア行事用保険に加入できますか? - A9. 加入できません。グループの構成員のみで行う懇親(親睦)行事は対象になりません。
- Q10. 建物内でバザーを開催します。参加者が不特定多数のため、参加者はCプラン、主催者であるスタッフは名簿の備付が可能なため、A1プランで加入することはできますか?
- A10. できません。主催者・参加者、全員同じプランでご加入いただくことになりますので、このケースの場合は全員Cプランでのご加入となります。
- Q11. 加入者が主催者ではない大規模なイベントに参加するため、加入者グループのみで保険に加入できますか?
- A11. 加入できません。当該制度は1イベント(行事)のすべての参加者を保険の対象に、主催者が加入しなければなりません。
- Q12. 弁当や食材を配送する場合や配布する場合は保険に加入できますか?
- A12. 弁当や食材を配送する場合は行事とはいえないため、ボランティア活動保険に加入してください。
- Q13. 施設内で行われる福祉まつりなど参加人数が把握できない行事の場合のCプランの加入条件について説明してください。
- A13. 参加人数が把握できない行事の場合はCプランでのご加入となりますが、①開催場所内外の区別が客観的に可能であること(フェンス等)②入口が特定されており、他からの入場ができないこと③入口において入場者が把握できることが加入の条件となります。
- Q14. 営利企業の社員が行うボランティア行事の取り扱いについて教えてください。
- A14. 営利企業(株式会社・有限会社等)の社員の勤務時間中に行われる行事や、勤務時間の前後に勤務時間と連続するかたちで行われる行事(企業が実施主体の行事)は、加入の対象外としていますが、企業活動と切り離された、企業内の有志の方々の自発的な活動によるボランティア行事は、加入の対象となります。企業内有志の方々の自発的な活動による行事の場合は、グループの代表を加入申込人としてください。(企業名での加入はできません。)
- Q15. 船を使用する日帰り行事に関する行事区分について、詳しく教えてください。
- A15.
<A1> ゴムボート遊び(川下りを除く)、ペダルボート、ボート教室(手漕ぎ) など <A2> プールで行うカヌー教室、船上パーティー、納涼船、ライン下り(観光用)、ヨット教室、遊覧船 など <A3> カヌー競漕、川で行うカヌー教室、クルーザー遊覧、ウェーブカッター、エイトボート、水上オートバイ <加入できない行事> いかだ下り、ライン下り(観光用以外)、ヨットレース、ラフティング、舟釣り(舟で釣り場に行くものを含みます。) など
行事用保険の補償範囲について
- Q16. キャンプで参加者が熱射病になりました。補償の対象になりますか。
- A16. 行事中に熱中症(日射病・熱射病)にかかった場合は、Aプラン・Bプラン・Cプランともに補償の対象となります。
- Q17. ボランティア行事用保険とボランティア活動保険に加入している参加者がケガをしました。両方の保険から保険金が支払われるのですか?
- A17. ケガをした参加者がボランティアとして行事に参加している場合、どちらの保険からも保険金が支払われます。
- Q18. お年寄りの交流会で配付したお弁当で食中毒が発生しました。補償されますか。
- A18. ケガの補償:細菌性・自然毒・化学物質、ウイルス性による食中毒とも補償されます。
賠償責任の補償:主催者側が提供した弁当が原因で食中毒が発生し、主催者が損害賠償責任を負われた場合には補償されます。 - Q19. 行事参加者が自家用車で他の参加者を迎えに行き、一緒に会場に向かいました。その際自動車事故を起こしてしまいましたが、対象となりますか?
- A19. ケガは補償の対象となります(通常の往復経路と認められる場合に限ります。)
ただし、自動車による対人・対物などの損害賠償責任や自身の自動車の修理代などは対象となりません。
福祉サービス総合補償に関するQ&A
加入手続きについて
- Q1. 「活動内容」欄の「活動従事者数」の記入要領を詳しく教えてください。
- A1. 「活動内容」欄には団体が行っているサービスの種類ごとに今年度の活動従事者数と前年度の延べ活動従事者数実績を記入します。
「今年度の活動従事者数」は活動従事者名簿に記載のある今年度活動予定の人の数を記入し、前年度延活動従事者数の計算方法は次の通りです。
◎前年度延活動従事者数=前年度の活動従事者全員の年間延活動実績日数合計
【例】毎日(年間365日)給食サービスを行っていたが、活動従事者数が次のような場合前年度延活動従事者数 年間365日のうち、活動従事者10人で活動した日が300日 10人×300日/年間=3,000人 年間365日のうち、活動従事者8人で活動した日が60日 8人× 60日/年間= 480人 年間365日のうち、活動従事者5人で活動した日が5日 5人× 5日/年間= 25人 合計 3,505人 - Q2. 前年度の延活動従事者数で加入となっていますが、新しく始めるサービスの場合は、どのように加入すればいいですか?
- A2. 前年度実績がない場合は、事業計画に基づく見込みの延活動従事者数を基に保険料を算出し加入してください。
福祉サービス総合補償の加入対象になりますか?
- Q3. 私たちの団体では、移送サービス事業を行っています。有償のため「ボランティア活動保険」は対象外なので、有償・無償を問わない「福祉サービス総合補償」に加入しようと考えますが、対象になりますか?
- A3. 対象となります。
ただし、自動車の所有・使用・管理に起因する賠償事故は、この保険では対象になりません。 - Q4. 「子供を預かり見守る」子育て支援サービスで、サービス提供者側の過失により子供にケガをさせた時、補償はどうなりますか?
- A4. サービス提供者側に損害賠償責任が発生する事故の場合、その過失割合に応じて、子供の治療費などが対人賠償保険金として支払われます。
- Q5. 福祉機器の販売・貸与をしている介護保険適用の団体ですが、加入対象になりますか?
- A5. 機器の販売は対象となりません。福祉用具(機器)の貸与のみの場合は対象となります。
- Q6. グループで市民後見人としての活動をしています。福祉サービス総合補償の対象になりますか?
- A6. 後見活動(業務)は、財産管理を行うなど24時間がその活動時間となり日常生活との区別が困難なため、福祉サービス総合補償では加入の対象にしていません。
- Q7. 就労継続支援施設の利用者の加入について
- A7. A型(雇用型) 利用者と雇用関係を結んでいるので活動従事者に含めて加入することが可能です。ただし、就労先での工事・製造・販売等といった福祉サービス以外の業務は対象となりません。B型(非雇用型) 利用者と雇用関係にないので、活動従事者に含めることはできません。
- Q8. 福祉サービス総合補償は、営利企業は加入できないのでしょうか?
- A8. 営利企業(株式会社・有限会社等)はご加入いただけません。企業としての事業活動となりますので、各種事業用の損害保険をご検討ください。
補償対象となる活動・補償範囲について
- Q9. 福祉サービス等の利用者が起こした賠償事故は補償の対象となりますか?
- A9. 利用者が起こした賠償事故は補償の対象となりません。
ただし、団体および活動従事者の管理責任を問われた場合は補償の対象となります。 - Q10. 家事援助サービス中、お年寄りからバッグと財布を預かり、買い物に行った際、何者かにバッグと財布を盗まれてしまいました。この場合、財布に入っていた現金は補償されますか?また、預った財布を紛失してしまった場合は補償されますか?
- A10. 補償されます。
サービス中に預った第三者の所有する財物を紛失したり盗難されたことによって、第三者に損害を与えた場合も補償の対象となります。(警察への届出が必要です。)
この場合、現金の損害については、補償限度額は各プランとも期間中10万円限度となります。 - Q11. 福祉サービスの活動に自動車を利用しています。その自動車を自宅と活動場所への往復にも利用していますが、往復途上の事故は補償されますか?
- A11. 活動従事者本人のケガについては、通常の往復経路であれば補償されます。
しかし、自動車による対人・対物などの賠償責任の補償は、往復途上、活動中を問わず補償対象外となります。 - Q12. ホームヘルプサービスを行っている団体です。活動に必要な会議や学習会も補償の対象となりますか?
- A12. 活動のための会議や学習会についても、それらを年間の活動日数に含めて加入した場合は対象となります。
送迎サービス補償に関するQ&A
送迎サービス補償の加入対象になりますか?
- Q1. 送迎サービスを行うサービス提供者を補償の対象として加入することができますか?
- A1. Aプランでは加入の対象となりません。
この制度は、送迎サービス利用者を補償の対象とするものであり、サービスの提供者を補償の対象として加入することはできません。
送迎サービスを行うサービスの提供者のケガの補償・賠償責任の補償は、「ボランティア活動保険」または「福祉サービス総合補償」に加入することで補償されます。
なお、Bプランについては、運転手を含む搭乗者全員が補償されます。 - Q2. AプランとBプランの両方に加入できますか?
- A2. 加入できます。両方に該当する事故の場合は、両方から補償されます。
- Q3. 有償にて送迎サービスを行っていますが、加入することができますか?
- A3. 有償にて送迎サービスを行っている場合でも、加入することができます。
ただし、Bプランでは、自家用自動車を対象としたプランとなっておりますので、営業用自動車(緑ナンバー)で送迎サービスを行っている場合は加入できません。 - Q4. 送迎サービス補償は、営利企業は加入できないのでしょうか?
- A4. 営利企業(株式会社・有限会社等)はご加入いただけません。企業としての事業活動となりますので、各種事業用の損害保険をご検討ください。
- Q5. 自動車を使用せずに電車やバスによる移動支援サービスを行いますが、加入できますか?
- A5. Aプランは加入できます。Bプランは特定した自動車に搭乗中のみの補償となりますので、加入できません。
補償対象となる活動・補償範囲について
- Q6. 送迎サービス利用者が起こした賠償事故は補償されますか?
- A6. 補償されません。
この制度では、送迎サービスの利用者または特定車両搭乗者(Bプラン)のケガのみが補償の対象となり、サービスの利用者やサービスの提供者が起こした賠償事故は補償されません。 - Q7. 送迎サービス補償に加入していますが、いつも使用している自動車が車検中のため代車で送迎していますが、補償はどうなりますか?
- A7. Aプランは代車でも送迎中であれば補償されます。ただし、Bプランの場合は、変更届出書にて事前にご通知ください。
- Q8. 私たちのボランティアグループでは、地域のお年寄りの送迎や移送のサービスを有償で始めることになりました。サービス中の事故が心配ですがどのような補償が必要ですか?
-
A8. サービス提供者側の補償と利用者側の補償が必要です。
①サービス提供者側の補償としては、「福祉サービス総合補償」があります。サービス提供者が活動中(活動場所への往復途上を含みます。)にケガをした場合の補償と活動中の偶然な事故により、サービス利用者や他の人の身体・財物に損害を与え、団体や活動従事者が法律上の損害賠償責任を負った場合の補償がセットになっています。なお、自動車の所有・使用・管理に起因する賠償事故は対象外ですので、自動車保険の加入の有無や加入内容についての事前の確認が必要です。
②利用者側の補償としては、「送迎サービス補償」があります。送迎中や移送中などに利用者がケガをした場合の補償です。加入プランとしては、利用者特定方式(Aプラン)と、自動車特定方式(Bプラン)があります。
●Aプランでは、管理下中の利用者がケガをした場合に補償されます。
●Bプランは、特定した自家用自動車に搭乗中のケガが補償されます。サービス利用者だけでなく運転者を含む搭乗者全員が補償されます。 - Q9. 買い物支援送迎サービスでサービス利用者の買い物中は補償の対象になりますか?
-
A9. 買い物中もボランティアが随行している場合は対象となりますが、サービス利用者が単独で買い物をしている間は対象となりません(Aプラン)。
Bプランは、特定した車両に搭乗中のみが対象です。
しせつの損害補償に関するQ&A
よくあるご質問(プラン1)
制度内容について
プラン1-① 基本補償(賠償事故)
- Q1. プラン1-①の見舞費用付補償(B型)の「傷害見舞費用」とプラン2「施設利用者の傷害事故補償」の違いについて教えてください。
-
A1. 利用者が施設内や管理下(加入施設外の就労実習中等を含む)にケガを被った場合、施設側の責任の有無に関わらず、両プランとも補償対象となります。プラン1-①見舞費用付補償(B型)の「傷害見舞費用」は施設にお支払いします。プラン2「施設利用者の補償」は利用者に直接お支払いします。
プラン1-①の「傷害見舞費用」とプラン2「施設利用者の補償」の主な相違点
プラン1-①(B型)[傷害見舞費用]
(目的)「事故発生後、すみやかに見舞金の手配をすることで、後に控える利用者側との交渉を円滑に進める」ためのプランです。- 事故発生後、施設側の〈法律上の賠償責任の有無〉を待つことなく、利用者の状態に応じて一定の見舞費用を施設へお支払いします。
- 施設側の〈法律上の賠償責任の有無〉が確定し、責任が「有」だった場合、すでにお支払いしている見舞費用を差引いた額の賠償保険金をお支払いします。逆に、責任が「無」だった場合は、見舞費用はそのままお受け取りいただくことができます。
プラン2-①②[施設利用者の補償]
(目的)「事故発生後も、利用者との良好な関係を維持し、事故の早期・円満な解決を図る」ためのプランです。- 事故発生後、施設側の〈法律上の賠償責任の有無〉を問わず、傷害保険金を利用者へお支払いします。
- 利用者がケガをされた場合、治療に要した入通院日数に対し、加入口数に応じた補償金額を直接利用者へお支払いします。
- 他の保険(賠償責任保険等)の支払いに関係なくお支払いすることができます。
- Q2. 「しせつの損害補償」プラン1-①と自動車保険の関係について教えてください。
- A2. 「しせつの損害補償」プラン1-①では「自動車の所有・使用・管理」に起因して生じた賠償責任については、保険金のお支払いの対象外となっています。(ただし「非所有自動車の賠償補償」は補償対象となります。)
一般的に「所有・使用・管理」とは自動車がおかれているすべての状況を意味しており、運行中のみならず、停車中や自動車が格納されているような状態なども該当することになります。
例えば、「停車している自動車に利用者を乗せドアを閉める際、利用者の手を挾んでしまいケガをさせてしまった」といった自動車の運行・運転に起因していないようなケースでも、自動車保険の補償対象となる場合もあります。
このように「しせつの損害補償」プラン1-①と自動車保険では補償する範囲を補完する関係になっており、その状況によって適用される保険の種類が異なることになります。 - Q3. 公立施設は、全国市長会、全国町村会の「総合賠償補償保険制度」と重複するということですが、自治体から委託されて運営をする施設が加入するとどのような場合に保険金が支払われますか?
- A3. 「しせつの損害補償」では自治体から委託された施設を運営する法人が法律上の賠償責任を負った場合、施設を運営する法人が負担すべき損害賠償金等をお支払いします。
※指定管理を受託された法人(施設)で、被保険者、保険金額(補償金額)についてのご相談は、福祉保険サービスまたは損保ジャパンまでお願いします。 - Q4. プラン1-①の身体賠償で対象となるのは、入所者や通所者等の利用者だけですか?
- A4. 利用者以外も対象となります。例えば入所者の家族、施設の出入り業者等が、施設に管理責任がある事故でケガをした場合などは賠償事故補償の対象となります。また、利用者が第三者に与えた損害により施設が管理責任を問われた場合も対象となります。ただし、役員・職員が業務中に被った身体障害に対する賠償責任は対象となりません。
- Q5. プラン1-①の対象となるのは施設内の事故だけですか?
- A5. 施設外での事故でも施設に管理責任があるかぎり、対象となります。例えば、施設外で引率する職員の不注意により利用者にケガを負わせた場合などはお支払いの対象となります。
- Q6. プラン1-①の見舞費用付補償(B型)において「入所利用者」と「通所利用者」それぞれが存在する時に「通所利用者」のみ加算して加入することは可能ですか?
- A6. 「入所利用者」のみあるいは「通所利用者」のみを加算して加入することはできません。
見舞費用付補償(B型)加入時はプラン1-①の合計定員数を加算してご加入ください。 - Q7. 職員(ボランティアスタッフを含みます。)の所有物(被服、眼鏡等)が施設利用者のいたずらや介助中の事故で壊れた場合に補償されますか?
- A7. 原則として職員の所有物の管理責任は職員の方にありますので、この制度の中では補償の対象となりません。
ただし、職員用ロッカーの不具合で施設利用者がいたずらして職員の私物を壊した場合など、施設側の管理責任が問われる場合にかぎってはプラン1-①で補償するケースもあります。 - Q8. 「保険金をお支払いできない主な場合」にある、医師・看護師等の専門職業人の行う医療行為等の専門的職業行為とはどのような行為を指すのでしょうか?
- A8. 専門職業人とは、その資格がなければ業務を行うことが法律によって禁止されており、行った場合の罰則が定められている資格を有する個人と定めております。
具体的には医師・看護師の他に弁護士、税理士、薬剤師、建築士、獣医師、司法書士、公認会計士、柔道整復師、理学療法士、作業療法士などが専門職業人にあたり、その資格業務が専門的職業行為となります。
なお、介護福祉士や社会福祉士、介護支援専門員は専門職業人にはあたりません。 - Q9. 認定特定行為業務従事者による、「たん吸引」および「経管栄養」は、保険金をお支払いできない主な場合(P.16、P.20)に記載の医療行為に該当しますか?
-
A9. 「たん吸引」および「経管栄養」は、医療行為に該当しますが、平成24年4月1日の「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、一定の条件のもとに行う「たん吸引」および「経管栄養」による損害賠償責任にかぎり補償の対象になります。具体的には医療や看護との連携による安全確保が図られていること等とありますが、詳細は「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」をご確認ください。
1.医療関係者との連携に関する基準
- 介護福祉士等が喀痰吸引等を実施するにあたり、医師の文書による指示を受けること。
- 医師・看護職員が喀痰吸引等を必要とする方の状況を定期的に確認し、介護福祉士等と情報共有を図ることにより、医師・看護職員と介護福祉士との連携を確保するとともに、適切な役割分担を図ること。
- 喀痰吸引等を必要とする方の個々の状況を踏まえ、医師・看護職員との連携の下に、喀痰吸引等の実施内容等を記載した計画書を作成すること。
- 喀痰吸引等の実施状況に関する報告書を作成し、医師に提出すること。
- 喀痰吸引等を必要とする方の状態の急変に備え、緊急時の医師・看護職員への連絡方法をあらかじめ定めておくこと。
- 喀痰吸引等の業務の手順等を記載した書類(業務方法書)を作成すること。
2.喀痰吸引等を安全・適性に実施するための基準
- 喀痰吸引等は、実地研修を修了した介護福祉士等に行わせること。
- 実地研修を修了していない介護福祉士等に対し、医師・看護師等を講師とする実地研修を行うこと。
- 安全確保のための体制を整備すること(安全委員会の設置、研修体制の整備等)。
- 必要な備品を備えるとともに、衛生的な管理に努めること。
- 上記1.③の計画書の内容を喀痰吸引を必要とする方又はその家族に説明し、同意を得ること。
- 業務に関して知り得た情報を適切に管理すること。
(注)病院・診療所は、医療関係者による喀痰吸引等の実施体制が整っているため、喀痰吸引等の業務を行う事業所の登録対象としない。
- Q10. 母子生活支援施設の定員数は世帯数ですか?それとも、子どもを含めた入所者数ですか?
- A10. 子どもを含めた入所者数を定員としています。
- Q11. 近隣の社会福祉法人3法人が協働して、地域における公益的な取組として相談事業を実施する場合の申込み方法を教えてください。
- A11. 「地域における公益的な取組」はオプション1「訪問・相談等サービス補償」で補償対象とすることができますが、活動中に利用者等に損害を与えた場合など、その関り方や事故の形態によって法律上の損害賠償のあり方の解釈が異なることがあります。
そのため、複数法人が協働して事業を実施する場合は、各法人がそれぞれオプション1に加入することが望ましいと考えます。
詳細については福祉保険サービスにお問い合わせください。 - Q12. 「法律上の賠償責任を負った場合」の解釈について教えてください。
- A12. 民法でいう過失責任に基づくもので、被保険者に過失がある場合です。過失とは、事故の発生を予見することができたのに注意をしなかった、またはこれを回避することをしなかったこと(義務を怠ったかどうか)をいいますが、予見することができたかどうかについての判断は、その時の態様によって異なりますので、事故が発生した場合にはすみやかに損保ジャパンに照会してください。
- Q13. レクリエーションのため近くの公園に行く途中、利用者の一人が車の所有者宅の前に駐車してあった車に傷をつけてしまいました。車の持ち主から施設に賠償請求がされましたが補償されますか?
- A13. 利用者が故意または過失によって自動車を傷つけたとすると、利用者本人がその損害賠償責任を負うのが原則です。利用者本人が不法行為責任を負う場合、社会福祉施設(社会福祉法人)が責任を負う事故かどうかにより補償の有無が決まります。事故が発生した場合にはすみやかに損保ジャパンに照会してください。
- Q14. 施設入居者が施設内で、施設訪問中の第三者にケガを負わせた場合、賠償の対象になりますか。また、施設外の施設行事中に利用者が参加者等にケガを負わせた場合にはどうですか?
- A14. 施設側に法律上の賠償責任が発生すれば、お支払いの対象となります。施設外での施設行事中も同様の考え方です。(賠償責任の発生有無は個別の事例によって異なります。)事故が発生した場合にはすみやかに損保ジャパンまで照会してください。
- Q15. 施設職員(介護福祉士)が施設利用者の服薬の手伝いを行い、分量を間違って服用させてしまいました。このため、利用者は腹痛等の症状がひどく数日間入院しました。この場合、補償の対象となりますか?
- A15. 施設職員が分量を間違ってしまったことが過失ありと判断され、法律上の賠償責任が発生する場合には、補償の対象となります。事故が発生した場合にはすみやかに損保ジャパンまで照会してください。
- Q16. 介護老人保健施設や介護医療院は加入できますか?
- A16. 同一法人が運営する他の福祉施設(特別養護老人ホーム、デイサービスセンターなど)がプラン1-①に加入していることを条件に、加入の対象としています。介護老人保健施設や介護医療院単独での加入はできません。また、併設の福祉施設と一緒にご加入いただいた場合でも、介護老人保健施設や介護医療院の医療行為等に関わる事故はお支払いできません。(介護に関わる事故のみ補償します。)
- Q17. グループホーム・有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅は加入の対象となりますか?
- A17. 同一法人が運営する他の福祉施設(特別養護老人ホーム・デイサービスセンターなど)がプラン1-①に加入していることを条件に、加入の対象としています。グループホーム・有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅は単独での加入はできません。
- Q18. 施設職員が利用者の衣服に補聴器・メガネなどがポケットに入ったまま気づかず洗濯し、破損させてしまった場合は補償の対象になりますか?
- A18. 施設職員がポケットの中身をチェックせずに洗濯したことが過失ありと判断され、法律上の賠償責任が発生する場合には、補償の対象となります。
- Q19. 施設の運営を手伝ってくれるボランティアや業務補助者(以下「ボランティアスタッフ等」といいます)についてはプラン1-①ではどう取り扱われますか?
- A19. 施設の指導・監督下にあるボランティアスタッフ等の行為については施設職員と同様に解釈します。ボランティアスタッフ等のミスで生じた事故について施設の賠償責任が問われた場合には、この保険で補償します。
(可能性は高くありませんが、ボランティアスタッフ個人に対して賠償請求訴訟等が提起されることも考えられます。この場合にはこのプランでは補償できません。) - Q20. 施設が貸し出した車いすを使用中、利用者が車いすに手を挟んでケガをしました。この場合、補償の対象となりますか?
- A20. 利用者の状態に合わせた車いすの使用上の説明が不足していた場合や、整備不良など施設管理上の不備があり、施設側に法律上の賠償責任が発生した場合には、補償の対象となります。
- Q21. 就労支援の施設利用者が、受入れ先企業で起こした賠償事故は、プラン1の基本補償の支払対象になりますか?
- A21. 受入れ先企業での事故の責任は、原則、管理下である受入れ先企業にありますので、しせつの損害補償の支払対象にはなりません。ただし、職員が同行指導していた場合や、加入施設が賠償責任を負った場合など、対象になることもあります。
- Q22. 施設内にある食堂で委託会社が作り提供した飲食物で施設利用者に食中毒事故が発生した場合、プラン1の基本補償で支払対象になりますか?
- A22. 委託会社への外注でも原則施設側の責任は免れず、支払対象になります。ただし、保険金支払い後に損保ジャパンが委託業者に求償します。
- Q23. 基本補償「事故対応特別費用」で特定感染症発生時の各種費用が補償されますが、具体的に対象となる特定感染症は?
-
A23. 特定感染症とは、「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条に規定する一類・二類および三類感染症をいいます。特定感染症に該当する感染症は以下の通りです。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、SARS(重症急性呼吸器症候群)、鳥インフルエンザ(H5N1型およびH7N9型のみ)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
プラン1-② 個人情報漏えい対応補償
- Q1. 個人情報漏えい対応補償の対象となる「個人情報」とは何か詳しく教えてください。
-
A1. 個人に関する情報であって、次の①または②のいずれかに該当するものをいいます。
- その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(注)により特定の個人を識別することができるもの。なお、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。
- 個人識別符号が含まれるもの
- (注)その他の記述等
文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号を除きます。
- Q2. 個人情報の記載された書類を紛失してしまいました。どのような補償が対象となりますか?
- A2. 個人情報が紛失した場合や行方不明になった場合は「情報漏えいのおそれがある場合」に該当し、費用保険金等が補償の対象となります。
- Q3. 社会福祉法人で介護老人保健施設、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅を運営していますが、加入できますか?
- A3. 加入できます。(病院は加入できません。)ただし、これらの施設のみの単独加入はできません。
- Q4. 「しせつの損害補償」のプラン1-①「基本補償」に加入していますが、それとの違いは何ですか?
-
A4. 「しせつの損害補償」のプラン1-①「基本補償」で補償される人格権侵害ならびに宣伝障害は右記の通りです。
個人情報漏えい事故は、名簿流出等が主な原因と考えられますので人格権侵害とは別に考えなくてはなりません。よってそのような事故に対応するためにはプラン1-②「個人情報漏えい対応補償」の加入が必要です。人格権侵害 - 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉き損
- 口頭、文章、図画その他これらに類する表示行為による他人の誹謗または他人の商品、製造物もしくは役務の中傷
- 口頭、文章、図画その他これらに類する表示行為による個人のプライバシーの権利の侵害
宣伝障害 - 口頭、文章、図画その他これらに類する表示行為による他人の誹謗または他人の商品、製造物もしくは役務の中傷
- 口頭、文章、図画その他これらに類する表示行為による個人のプライバシーの権利の侵害
- 著作権、標題または標語の侵害
- 宣伝上の着想または営業の手法の不正な流用
- Q5. 法人全体で加入しますが、会計上施設ごと別々に加入したいのですが、施設単位での加入は可能ですか?
- A5. 加入依頼書を施設単位に分割し、加入することもできます。ただし、保険料は割高になります。
プラン1-③ 施設の什器・備品損害補償
- Q1. 施設の現金等も補償の対象となっていますが、職員が銀行、行事先など施設外へ持ち出した場合の補償はどうなりますか?
- A1. 持ち出し中に現金を盗難されてしまった場合は、お支払いの対象となります。(警察への届け出がある場合にかぎります。)ただし、その際、持ち出した金額が確認できる客観的な資料が必要です。また、置き忘れ、紛失等は補償の対象になりません。
- Q2. 国内出張で職場のノートパソコンを不意に落とし壊してしまいました。補償の対象になりますか?
- A2. 一時的に事務所外に持ち出された什器・備品も補償の対象となります。ただし、パソコンに保存していたデータの損失による損害は補償の対象になりません。
よくあるご質問(プラン2)
制度内容について
プラン2-① 入所型施設利用者の傷害事故補償
- Q1. 傷害事故補償の対象となるのは、入所者だけですか?
- A1. 入所者だけが対象です。入所者への訪問客(家族を含みます。)、施設管理者の同居の親族・施設職員・納入業者・デイサービス等通所型施設利用者は補償の対象となりません。
- Q2. 知的障害者のケガは、お支払いできない事故の「疾病・脳疾患または心神喪失による傷害」に該当し、補償が受けられないのですか?
- A2. 補償対象者である知的障害者の方が疾病や脳疾患を抱えていても、症状が固定した状態で、単純に階段や廊下でバランスをくずし、転倒した場合等は保険金のお支払対象となります。
しかし、薬を飲み忘れた等の原因により、疾病の症状が悪化し発作等により転倒した場合は、保険金をお支払いできない主な場合の「疾病・脳疾患または心神喪失による傷害」に該当するため、お支払いの対象にはなりません。
疾病による事故かそうでないか判断が難しいケースは、既往症や事故状況などの詳細を確認したうえで、損保ジャパンの保険金サービス課までご照会ください。 - Q3. 入所施設の利用者が施設から外出し、施設外にてケガをした場合、補償の対象となりますか?
- A3. 外出して、施設の管理下から外れる場合、補償の対象となりません。ただし、利用者が徘徊により行方不明になった場合や、施設職員に伴われて外出している場合、利用施設以外の施設に社会復帰訓練として単独外出した際の往復途上の事故については、補償の対象となります。
プラン2-② 通所型施設利用者の傷害事故補償
- Q1. デイサービスを受け自宅へ帰ろうとしたが、急に思いたち、逆方向の親戚の家へ向かいその経路で交通事故に遭いました。補償の対象となりますか?
- A1. 親戚の家へ向かった時点から、デイサービス利用とは別目的のための行動となり、往復途上とは認められず補償の対象となりません。
- Q2. 「利用者の自宅との往復途上における事故」の補償について詳しく教えてください。
- A2. 「利用者の自宅との往復途上における事故」については、自宅敷地内を出てから自宅敷地内にもどるまでの往復途上が補償の対象です(通常経路が対象)。ただし、施設職員が業務として同行している場合は、通常経路外および自宅敷地内においても管理下中として補償の対象となります。
※不特定多数利用者施設の場合、施設来場中の傷害(ケガ)にかぎられるため往復途上は補償対象外です。 - Q3. 利用者が地元の企業に訓練(実習)に行きます。プラン2-①および②の補償範囲はどのようになるのでしょうか。
- A3. 就労継続支援または就労移行支援等において、支援を目的として利用者に加入施設外に出向いてもらい、別の社会福祉施設等の受入先で就労実習や作業等を行っている間および当該受入先施設との往復途上の事故も補償の対象となります(ただし、加入法人の管理下であると合理的かつ客観的に判断できる場合(注)にかぎります。)。
(注)シフト表や利用者の個人記録などにおいて、利用者名・受入先名・日程・作業時間・作業内容などが客観的かつ事前に把握できている状態や、職員が帯同している間の状態を示します。なお、受入先と加入法人間との契約有無は問いませんが、受入先と利用者間で個別に雇用契約が締結される場合は加入法人の管理下とはなりません。 - Q4. 老人福祉施設ですが、新たに地域包括支援センターと介護予防の相談・アドバイスを行う事業を実施することになりました。
現在プラン1-①の基本補償、プラン2の施設利用者の補償に加入していますが、センター利用者のケガなどの事故に備えるには、何か手続きが必要ですか? - A4. 地域包括支援センターおよび介護予防の相談・アドバイスを行う事業に関わる、利用者のケガなどの事故に備えるためにはプラン2-②の不特定多数利用者施設の傷害事故補償に加入してください。保険料は年間利用予定者数(延べ人数)をもとに計算します。
また、賠償責任保険については、プラン1-①の基本補償では施設業務(サービス)以外の事業は補償対象とならないためプラン1-①オプション1訪問・相談等サービス補償に加入する必要があります。 - Q5. 職員を伴いバスを利用して一泊の懇親旅行に行きますが、ホテルに宿泊する場合、プラン2-②の「通所型施設利用者の傷害事故補償」で、ホテル内で発生した傷害事故は補償されますか?
- A5. 原則、宿泊中の傷害事故は補償の対象になりません。ただし、宿泊中を管理下と見なすことができる特段の事情がある場合を除きます。
- Q6. デイサービス利用者の家族(または利用者本人)が自家用車で、数人のデイサービス仲間宅に立寄りし、仲間も同乗した上でデイサービスへ向かっている途中で事故に遭いました。
プラン2-②「通所型施設利用者の傷害事故補償」とプラン2-③「施設の送迎車搭乗中の傷害事故補償」に法人が加入していますが、補償の対象となりますか? - A6. プラン2-②「通所型施設利用者の傷害事故補償」では、自宅と施設間の往復途上(合理的な経路により往復している間)と確認できる場合、補償の対象となります。
プラン2-③「施設の送迎車搭乗中の傷害事故補償」は、送迎サービスに使用する、予め特定自動車報告票で定めた自動車に搭乗中の傷害事故が補償の対象となるため、特定されていない自家用車に搭乗中の事故は補償の対象となりません。
プラン2-③ 施設送迎車搭乗中の傷害事故補償
- Q1. 同一法人ですが、特別養護老人ホームとデイサービスセンターを施設単位で別々に加入しています。当該法人では1台の送迎車を両施設で併用していますが、この場合、両方の施設でそれぞれに加入する必要がありますか?
- A1. どちらか一方の施設でご加入いただければ大丈夫です。
プラン2-③「施設の送迎車搭乗中の傷害事故補償」は、時間、場所を問わず、その車両に搭乗中の方(運転手など職員も含む)がケガをした場合に補償の対象となります。 - Q2. デイサービスに向かう途中、施設送迎車の運転手の過失で他の自動車に追突し、搭乗中の利用者3人がケガを負いました。プラン1-①、2-②、2-③に加入していますが補償はどうなりますか?
- A2. プラン1-①は自動車に起因する事故は補償の対象になりません。
プラン2-②、2-③は補償の対象となります。したがって、プラン2-②、プラン2-③の両方に加入していた場合はプラン2-②とプラン2-③の両方から保険金が支払われます。
よくあるご質問(プラン3)
制度内容について
プラン3-① 職員の労災上乗せ補償
- Q1. プラン3-①「職員の労災上乗せ補償」ではアルバイト・パートタイマーなどの臨時雇用職員も対象となりますか?
- A1. 政府労災保険の対象は労働者(賃金支給)となっていますので、政府労災保険の加入者であれば、アルバイト・パートタイマーなどの臨時雇用職員についても補償の対象となります。
※直近会計年度(4月1日加入の場合は令和3年7月)の政府労災申告書記載の労働者数で加入してください。 - Q2. 加入に必要な確認事項に、法定外補償規定の備付けの有無がありますが、一体どういうものかを、具体的に教えて欲しいのですが。
- A2. 法定外補償規定は、被用者に対し政府労災保険給付のほかに、法人(施設)が独自に一定の災害補償を行うことを目的とするものを言います。
右ページには法定外補償規定例を掲載しておりますのでご参照ください。 - Q3. 政府労災やプラン3-①「職員の労災上乗せ補償」とプラン3-①オプション「使用者賠償責任補償」との違いは何ですか?
- A3. 政府労災は、財産的損害を対象とした最低限の補償であり、これに一定の補償を上乗せするのがプラン3-①職員の労災上乗せ補償です。労災民事訴訟制度では、被災労働者またはその遺族は、慰謝料などの精神的損害を含む全損害の賠償を求めることができます。こうした慰謝料などの精神的損害を含む賠償にも対応することができるのが、プラン3-①オプションの使用者賠償責任補償の特長です。
プラン3-② 役員・職員の傷害事故補償
- Q1. プラン3-②「役員・職員の傷害事故補償」にアルバイト、ボランティア(業務補助者)は加入できますか?
また、このプランで加入できる役員の範囲(例えば理事長、理事など)について教えてください。 - A1. アルバイト(臨時雇用職員)、ボランティア(業務補助者)も加入できます。
また、理事長や理事なども当該法人に勤務している実態があればご加入できます。 - Q2. 施設業務繁忙中に突然脳疾患で倒れ、数時間後死亡した場合、補償はどのようになりますか?
- A2. プラン3-①(職員の労災上乗せ補償)
政府労災保険の給付の対象になった場合は、補償の対象となります。
プラン3-②(役員・職員の傷害事故補償)
脳疾患は、ケガではなく疾病に該当しますので、補償の対象となりません。
プラン3-③ 役員・職員の感染症罹患事故補償
- Q1. 3-③「役員・職員の感染症罹患事故補償」では、新型インフルエンザは補償対象となりますか?
- A1. 3-③役員・職員の感染症罹患事故補償では新型インフルエンザは補償対象となりません。補償対象となるのは、手引P.64に記載している感染症のみです。
プラン3-④ 雇用慣行賠償補償
- Q1. 3-④「雇用慣行賠償補償」で対象となる労働トラブルの対象者は正職員のみですか?
- A1. 正職員に対しての損害賠償金だけでなく、アルバイト・パートタイム職員・派遣職員・他法人への出向者・他法人からの受け入れ職員も対象となります。
よくあるご質問(プラン4)
制度内容について
プラン4 社会福祉法人役員等の賠償責任補償
- Q1. 対象役員等を限定して加入することはできますか?
- A1. 対象役員等を限定して加入することはできません。社会福祉法人の役員等全員でご加入いただくことになります。
- Q2. 訴訟に勝訴した場合は保険金の支払いはないのでしょうか?
- A2. 訴訟に勝訴した場合は損害賠償金のお支払いはできませんが、訴訟に要した弁護士費用などの争訟費用はお支払いの対象となります。
- Q3. 故意・重過失による行為に伴う損害賠償責任は、本プランの補償対象となりますか?
- A3. 役員等の業務としての行為が故意・重過失であることをもって、すぐに補償対象外となるものではありません。ただし、故意については、「保険金をお支払いできない主な場合」に掲載されている、「被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たこと」や、「法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為」などに該当する可能性が高く、お支払いの対象外となる可能性が高いと考えられます。
- Q4. 契約前の行為に起因する損害賠償請求は補償の対象になりますか?
- A4. 最初に損保ジャパンにてご契約いただいた契約の始期日から10年前までの行為に係る損害賠償請求は、補償の対象になります。ただし、最初に損保ジャパンにてご契約いただいた契約の始期日より前に、既に損害賠償請求がなされるおそれを認識していた場合、または既に損害賠償請求がなされている場合は、このかぎりではありません。
- Q5. 退任した役員・評議員は補償の対象になりますか?
- A5. 最初に損保ジャパンにてご契約いただいた契約の始期日において役員・評議員であった方であれば、損害賠償請求が提起された時に退任していても補償の対象になります。
- Q6. 役員Aさんによる職員Bさんへのパワハラに対して、適切な対処をとらなかったとして人事・労務担当役員のCさんが訴えられた場合、補償の対象となりますか?
- A6. 補償の対象となります。ただし、パワハラをした行為者である役員Aさん自身に対する損害賠償請求はお支払いの対象となりません。
- Q7. 万一、損害賠償請求がなされた場合、どのように対応すればいいのですか?
- A7. 社会福祉法人役員等の賠償責任補償では、損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、①損害賠償請求を最初に知ったときの状況、②申し立てられている行為、③原因となる事実関係、等についてただちに損保ジャパンへご連絡ください。事実関係を確認のうえ、適切なアドバイスおよび保険金請求のためのご案内をします。
保育所・認定こども園の損害補償に関するQ&A
よくあるご質問(プラン1)
- Q1. 「法律上の賠償責任を負った場合」の解釈について教えてください。
- A1. 民法でいう過失責任に基づくもので、被保険者に過失のある状況を示します。過失とは、事故の発生を予見することができたのに注意をしなかった、またはこれを回避しなかったこと(義務を怠ったかどうか)などをいいますが、これらの判断は、その時の状況によって異なりますので、事故が発生した場合にはすみやかに損保ジャパンに照会してください。
- Q2. 認可保育所で市町村から受託している学童保育は加入対象となりますか?
- A2. 「保育所の損害補償」の対象ではなく、「しせつの損害補償」の対象となりますので、別途「しせつの損害補償」の加入手続きが必要となります。
- Q3. 保育所で一時預かり事業をはじめますが、定員がない場合にはどのように加入したらよいですか?
- A3. 定員がない事業の場合には、プラン1-①オプション1地域子育て支援拠点事業等補償に年間事業収入に基づき加入することができます。
- Q4. 園庭開放して小学生に体操を教える事業を始める場合、プラン1-①基本補償の対象となりますか?
- A4. 当該事業が保育所の本来業務とならないためプラン1-①基本補償の対象となりませんが、当該事業についてオプション1地域子育て支援拠点事業等補償に加入することで補償対象とすることができます。
- Q5. プラン1-①基本補償の対象となるのは保育所敷地内の事故だけですか?
- A5. 保育所敷地内外を問わず保育所に賠償責任がある場合に対象となります。
- Q6. プラン1-①基本補償の身体賠償では、対象となるのは園児の事故だけですか?
- A6. 園児以外の第三者に対する事故も対象となります。
- Q7. 園外保育のため近くの公園に行く途中、園児の一人が駐車してあった自動車に傷をつけてしまいました。自動車の所有者から保育所に賠償請求がされましたがプラン1で補償されますか?
- A7. 園児が故意または過失によって自動車を傷つけた場合、園児(および親権者)が損害賠償責任を負うのが原則ですが、保育所として責任を負う必要があるかどうかは事故の状況によって異なります。事故が発生した場合にはすみやかに損保ジャパンに照会してください。
- Q8. 保育所の運営を手伝ってくれるボランティアや業務補助者(以下「ボランティアスタッフ等」といいます)についてはプラン1ではどう取り扱われますか?
- A8. 保育所の指導・管理下にあるボランティアスタッフ等の行為については保育所職員と同様に解釈します。ボランティアスタッフ等のミスで生じた事故について保育所の賠償責任が問われた場合には、プラン1で補償します。
- Q9. 外注先業者が製造した給食が原因で園児に食中毒が発生した場合、プラン1-①基本補償の対象となりますか?
- A9. 外注先業者が製造した給食が原因であっても保育所が法律上の賠償責任を負う場合が多く、その場合はプラン1-①基本補償の対象となります。ただし、保険金支払い後に損保ジャパンが外注先業者に求償します。
- Q10. 近隣の社会福祉法人3法人が協働して、地域における公益的な取組として相談事業を実施する場合の申込み方法を教えてください。
- A10. 「地域における公益的な取組」はオプション1「地域子育て支援拠点事業等補償」で補償対象とすることができますが、活動中に利用者等に損害を与えた場合など、その関り方や事故の形態によって法律上の損害賠償のあり方の解釈が異なることがあります。
そのため、複数法人が協働して事業を実施する場合は、各法人がそれぞれオプション1に加入することが望ましいと考えます。
詳細については福祉保険サービスにお問い合わせください。 - Q11. プラン1-①オプション3看護職の賠償責任補償において保険期間中に看護師の交替がありますが、手続きは必要ですか?
- A11. 令和5年度契約よりお手続きは不要となりました。
- Q12. プラン1-①オプション4クレーム対応サポート補償において近隣住民から苦情が発生し、対応が困難になりサポートを受けたい場合、どのような手続きが必要ですか?
- A12. 対象のクレームが発生した場合、専門相談窓口「クレームコンシェル」にご連絡ください。
詳細についてはP21をご参照ください。 - Q13. どのような個人情報がプラン1-②個人情報漏えい対応補償の対象となりますか?
マイナンバーは対象となりますか?また、プラン1-①基本補償では補償されませんか? - A13. 現に生存している個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものが対象となります。氏名、住所、生年月日等やマイナンバーも対象になります。
プラン1-①基本補償で補償される人格権侵害ならびに宣伝障害では、個人情報の漏えいに起因する損害については対象としていないため、プラン1-②個人情報漏えい対応補償の加入が必要となります。 - Q14. プラン1-③保育所の什器・備品損害補償では、保育所の現金等も補償の対象となっていますが、職員が銀行や行事先へ持ち出した場合の盗難時の補償はどうなりますか?
- A14. 持ち出し中の現金が盗難に遭った場合も補償の対象となります。(警察への届け出がある場合にかぎります。)
ただし、その際、持ち出した金額が確認できる客観的な資料が必要です。また、置き忘れ、紛失等は補償の対象となりません。 - Q15. プラン1-③保育所の什器・備品損害補償では、業務で外出中に職場のノートパソコンを落とし、破損した場合補償の対象となりますか?
- A15. 一時的に事務所外に持ち出された什器・備品も補償の対象となります。ただし、パソコンに保存していたデータの損失による損害は補償の対象となりません。
- Q16. 認定特定行為業務従事者による、「たん吸引」および「経管栄養」は、保険金をお支払いできない主な場合(P.16、P.20)に記載の医療行為に該当しますか?
-
A16. 「たん吸引」および「経管栄養」は、医療行為に該当しますが、平成24年4月1日の「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、一定の条件のもとに行う「たん吸引」および「経管栄養」による損害賠償責任にかぎり補償の対象になります。具体的には医療や看護との連携による安全確保が図られていること等とありますが、詳細は「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」をご確認ください。
1.医療関係者との連携に関する基準
- 介護福祉士等が喀痰吸引等を実施するにあたり、医師の文書による指示を受けること。
- 医師・看護職員が喀痰吸引等を必要とする方の状況を定期的に確認し、介護福祉士等と情報共有を図ることにより、医師・看護職員と介護福祉士との連携を確保するとともに、適切な役割分担を図ること。
- 喀痰吸引等を必要とする方の個々の状況を踏まえ、医師・看護職員との連携の下に、喀痰吸引等の実施内容等を記載した計画書を作成すること。
- 喀痰吸引等の実施状況に関する報告書を作成し、医師に提出すること。
- 喀痰吸引等を必要とする方の状態の急変に備え、緊急時の医師・看護職員への連絡方法をあらかじめ定めておくこと。
- 喀痰吸引等の業務の手順等を記載した書類(業務方法書)を作成すること。
2.喀痰吸引等を安全・適性に実施するための基準
- 喀痰吸引等は、実地研修を修了した介護福祉士等に行わせること。
- 実地研修を修了していない介護福祉士等に対し、医師・看護師等を講師とする実地研修を行うこと。
- 安全確保のための体制を整備すること(安全委員会の設置、研修体制の整備等)。
- 必要な備品を備えるとともに、衛生的な管理に努めること。
- 上記1.③の計画書の内容を喀痰吸引を必要とする方又はその家族に説明し、同意を得ること。
- 業務に関して知り得た情報を適切に管理すること。
(注)病院・診療所は、医療関係者による喀痰吸引等の実施体制が整っているため、喀痰吸引等の業務を行う事業所の登録対象としない。
- Q17. 基本補償「事故対応特別費用」で特定感染症発生時の各種費用が補償されますが、具体的に対象となる特定感染症は?
-
A17. 特定感染症とは、「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条に規定する一類・二類および三類感染症をいいます。特定感染症に該当する感染症は以下の通りです。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、SARS(重症急性呼吸器症候群)、鳥インフルエンザ(H5N1型およびH7N9型のみ)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
よくあるご質問(プラン2)
- Q1. プラン2-①園児の傷害事故補償では、園外保育の外出先での事故は補償の対象となりますか?
- A1. 対象になります。
園の内外を問わず保育所管理下での事故は対象となります。 - Q2. プラン2-①園児の傷害事故補償では、自宅との往復途上での事故は補償の対象となりますか?
- A2. 対象になります。
自宅(敷地)を出てから保育所に到着するまでの往路および保育所を出てから自宅(敷地)に到着するまでの復路での事故も対象となります(通常経路のみが対象)。 - Q3. プラン2-②来園者の傷害事故補償では、だれが補償の対象となりますか?
- A3. 地域子育て支援拠点事業等の利用者、保育所行事等に参加する保護者、取引先業者等園児以外で保育所に来訪する人を対象とすることができ、対象者の年間延べ来園者数に基づき加入します。
- Q4. プラン2-③園児送迎車搭乗中の傷害事故補償では、補償の対象となるのは園児だけですか?
- A4. 園児だけではありません。登録車両に搭乗している人全員(運転手や職員も含む)が対象となります。
- Q5. プラン2-③園児送迎車搭乗中の傷害事故補償では、遠足に行く際に送迎用バスを使用しますが、対象となりますか?
- A5. 対象になります。
通園以外の目的でも登録車両に搭乗している際にケガをした場合、補償の対象となります。
よくあるご質問(プラン3)
- Q1. プラン3-①職員の労災上乗せ補償では、アルバイト・パートタイマーなどの臨時雇用職員も対象となりますか?
- A1. 政府労災保険の対象は労働者(賃金支給)となっていますので、政府労災保険の加入者であれば、アルバイト、パートタイマーなどの臨時雇用職員についても補償の対象となります。直近会計年度の政府労災申告書に基づく労働者数で加入してください。
- Q2. 政府労災やプラン3-①職員の労災上乗せ補償とオプション使用者賠償責任補償との違いは何ですか?
- A2. 政府労災は財産的損害を対象とした最低限の補償であり、これに一定の補償を上乗せするのがプラン3-①職員の労災上乗せ補償です。また、被災労働者またはその遺族が慰謝料などの精神的損害を含む全損害の賠償を求める場合にも対応することができるのが、使用者賠償責任補償の特長です。
- Q3. プラン3-②役員・職員の傷害事故補償にアルバイト、ボランティア(業務補助者)は加入できますか?
- A3. アルバイト、ボランティアも加入できます。また、保育所(法人)に勤務している理事(理事長を含む)も加入することができます。前年度の延べ出勤日数に基づき加入してください。
- Q4. プラン3-③役員・職員の感染症罹患事故補償では、特定の職員のみで加入することはできますか?
- A4. 常勤役員、常勤職員のみを対象とするA型、およびA型に非常勤役員、非常勤職員を加えたB型の2タイプから選択いただけますが、一部の役員・職員のみで加入することはできません。なお、派遣職員、実習生、業務補助者(ボランティア等)は対象となりません。
- Q5. プラン3-④「雇用慣行賠償補償」で対象となる労働トラブルの対象者は正職員のみですか?
- A5. 正職員に対しての損害賠償金だけでなく、アルバイト・パートタイム職員・派遣職員・他法人への出向者・他法人からの受け入れ職員も対象となります。
よくあるご質問(プラン4)
- Q1. 対象となる役員等を限定して加入することはできますか?
- A1. 役員等(理事、監事、評議員、管理職従業員)全員を対象としているため、役員を限定して加入することはできません。
- Q2. 故意・重過失による行為に伴う損害賠償責任は補償の対象となりますか?
- A2. 故意・重過失による行為に伴うものが全て補償対象外になるとはかぎりません。ただし、故意については「被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たこと」や「法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為」などに該当する場合は対象外となります。
- Q3. プラン4に加入する前の行為に起因する損害賠償請求は補償の対象となりますか?
- A3. 最初に本プランに加入した契約の始期日から10年前までの行為に起因する損害賠償請求は補償の対象になります。ただし、その時点で既に損害賠償請求がなされるおそれを認識していた場合、または既に損害賠償請求がなされている場合は、このかぎりではありません。
- Q4. 退任した役員等は補償の対象となりますか?
- A4. 最初に本プランに加入した契約の始期日において対象であった役員等であれば、損害賠償請求が提起された時点に退任していても補償の対象になります。
- Q5. 役員Aさんによる職員Bさんへのパワハラに対して、適切な対処をとらなかったとして人事・労務担当役員のCさんが訴えられた場合、補償の対象となりますか?
- A5. 補償の対象となります。ただし、パワハラをした行為者である役員Aさん自身に対する損害賠償請求は補償の対象となりません。
※このページは概要を説明したものです。
詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。